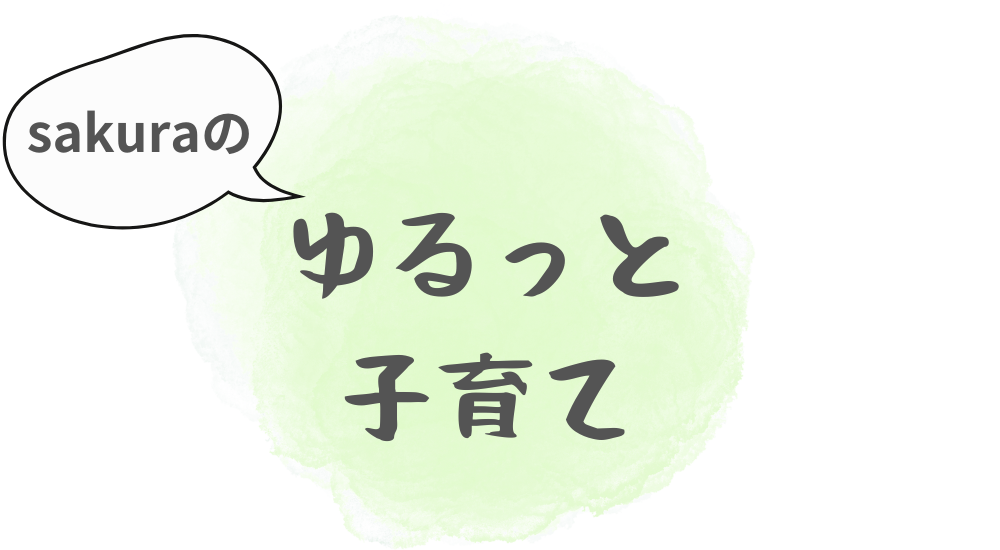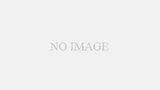こんにちわ。sakuraです。
この前、保育園から「今年度より、夏季プールを中止します。」と連絡がありました。
小学校からは「夏休み期間のプール開きは中止です」と連絡がありました。
えぇ!子供達が毎年楽しみにしていたのに!と衝撃でしたが、先生方もなくなく決断したそうです。
お話をきいたことを少し書いていこうとおもいます。
保育園のプールの目的

1.水に親しむ
水遊びを通じて、幼児が水に対する恐怖心を取り除き、楽しく水に慣れることを目的としています。
2.感覚の発達
水の感触や温度の変化など、五感を刺激することで、感覚の発達を促します。
3.身体発達の促進
水中での動きは体のバランス感覚を養い、全身の筋肉を使うことで、運動能力の基礎を作ります。
4.社会性の発達
水遊びを通じて、友達と一緒に遊ぶ楽しさを学び、協調性やコミュニケーション能力を育てます。
5.安全教育の基礎
基本的な水の安全性に関する意識を少しずつ身につけさせることが目的です。例えば、水に入る前の準備運動や、危険な行動をしないことなどを教えます。
小学校のプールの目的

1.水泳技術の習得
基本的な泳ぎ方(クロール、平泳ぎ、背泳ぎなど)を学び、水中での自信と安全を身につけることが目的です。
2.体力向上
水泳は全身運動であり、体力や筋力の向上を促します。特に心肺機能の強化に役立ちます。
3.水の安全性教育
溺れないための基本的な知識や、水辺での安全な行動を学びます。これは特に日本のような海や川が多い国では重要です。
4.健康増進
規則的な運動を通じて、健康的なライフスタイルを促進します。また、ストレスの軽減にも役立ちます。
5.協調性と社交性の育成
水泳の授業を通じて、クラスメイトとの協力やコミュニケーションスキルを育てます。

両者とも、水を通じた身体的および社会的な発達を重視していますが、年齢に応じた適切な教育内容や活動が計画されています。
なぜ、プール開きをする園・学校が減っているの?

1. 安全面の懸念
- 事故のリスク: プールでの事故やケガが懸念され、安全管理の負担が大きくなっています。水難事故やプールでの怪我に対する責任が重く、リスクを避けるためにプール開きを見送る施設が増えています。
- 感染症のリスク: プールは水を介した感染症のリスクがあるため、衛生管理が厳しく求められます。特に新型コロナウイルス感染症の影響で、感染リスクを最小限に抑えるためにプール利用を控える傾向があります。
2. メンテナンスとコスト
- 維持費用の増加: プールの維持管理には定期的な清掃や水質管理、設備の点検などが必要です。これらのコストが年々増加しており、予算の制約からプールを閉鎖する学校や園が増えています。
- 老朽化: 古いプールの設備が老朽化し、修繕や改修が必要になることが多いですが、その費用を捻出できないために閉鎖するケースがあります。
3. 気候変動
- 気候変動の影響: 日本の夏は年々暑さが厳しくなっており、熱中症のリスクが高まっています。そのため、屋外プールでの活動が危険視されることがあります。また、異常気象や大雨による影響でプール開きが難しくなる場合もあります。
4. プログラムの多様化
- 教育プログラムの変更: 学校や保育園の教育プログラムが多様化し、水泳教育以外の活動や授業内容に重点が置かれることが増えています。限られた時間とリソースの中で、他の学習活動に優先順位を置く傾向があります。
- 代替施設の利用: 一部の学校や保育園では、公共の屋内プールやスポーツクラブのプールを利用することで、自前のプールを必要としなくなっています。
5. 人材の確保
- 専門スタッフの不足: プールの安全管理や指導には専門的な知識と技術が求められますが、これを担うスタッフの確保が難しいことが増えています。特に地方では人材不足が深刻です。

これらの要因が重なり、プール開きを行う園や学校が減少している現状があります。それぞれの施設は安全管理や費用対効果を考慮し、プールの利用方法や代替策を模索しています
プール開きの代替案はあるの?

1. 公共のプールや民間施設の利用
- 公共プールの利用: 学校や保育園が近隣の公共プールを借りて水泳指導を行うケースがあります。これにより、自前のプールの維持管理コストを削減できます。
- スポーツクラブやジムのプール: 民間のスポーツクラブやフィットネスジムと提携し、そこのプールを利用することで専門的な指導と安全管理が受けられます。
2. 水遊びや水に関連した活動
- ウォーターテーブルや噴水設備: 小規模な水遊び用設備を設置することで、幼児が水に触れる機会を提供します。これにより、水への親しみを持たせつつ、安全に遊べる環境を提供できます。
- シャワープレイ: 庭や校庭に設置したシャワー設備で、水遊びを楽しむ活動を行うことができます。これにより、プールほどの安全管理が必要なく、手軽に水遊びが可能です。
- 泥遊び:泥水の感触や温度の変化などで、五感を刺激することができます。

圧の強すぎない散水ホースを使ってシャワー遊びをしたり、泥遊びをしたりして水に触れる機会を作っています。
日影を作ったり水分補給で熱中症対策も忘れず行っています。
3. 水泳教室や水泳キャンプ
- 短期水泳教室: 夏休みや長期休暇を利用して、外部の水泳教室に参加するプログラムを提供することがあります。これにより、専門のインストラクターから集中的に指導を受けることができます。
- 水泳キャンプ: 夏季休暇中に数日間の水泳キャンプを開催し、集中的に水泳技術を学ぶ機会を提供します。これにより、自然の中での活動と水泳の両方を体験できます。
これらの代替案は、それぞれの施設の環境や予算に応じて選ばれることが多く、子どもたちに水に親しむ機会を提供しつつ、安全性と効率性を確保するための工夫がされています。
プール開き現象の理由は、安全性確保の為だった!

本当は、暑い日が続いているからプールに入れてあげたいんだけど、熱中症リスクや人材確保が難しくて……

プールの管理や老朽化問題もあって、近年は近くのプール施設にバス移動で利用しているんです。

近年、プールに水をつけるのが怖い。肌荒れが気になる等の理由で、プールに入らない子も数人いるんです。
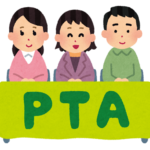
小学校では、PTA役員の確保や緊急時の対応を考えると、年々夏休みのプール開きが難しくなってきています

先生方も、子供達の安全を思っての判断なんですね!
感謝しかありません!
いかがでしたでしょうか?
この記事を振り返り、家庭でも安全面に気を付けながら、
- スイミングスクールに通う
- 公共施設のプールに遊びに行く
- 庭先で水遊びをする
このようなことを考えないとな…と思いました。
何せ、負担なく、楽しくできるといいですよね!